二十四節気(にじゅうしせっき)とは、一年を四つの季節(春・夏・秋・冬)に分けさらに、それぞれの季節を六つに分け、それぞれに名前を付けて季節を現した物です。
元は、中国の太陰暦を元に作られ、また現在の暦と太陰暦とのずれもあるために現在の季節感とはかなり違和感がある所もありますが、現代日本でも広く使われている言葉も多数あります。
本来であれば、ある程度の期間(10日から2週間程度)の間を現す言葉ですが、現在では特定の日をさして使われることが多くなっています。現代のカレンダーでの日時は国立天文台が発表した日時を記載してあります。
二十四節気の言葉
春の言葉
立春(りっしゅん)・雨水(うすい)・啓蟄(けいちつ)
春分(しゅんぶん)・清明(せいめい)・穀雨(こくう)
夏の言葉
立夏(りっか)・小満(しょうまん)・芒種(ぼうしゅ)
夏至(げし)・小暑(しょうしょ)・大暑(たいしょ)
秋の言葉
立秋(りっしゅう)・処暑(しょしょ)・白露(はくろ)
秋分(しゅうぶん)・寒露(かんろ)・霜降(そうこう)
冬の言葉
立冬(りっとう)・小雪(しょうせつ)・大雪(だいせつ)
冬至(とうじ)・小寒(しょうかん)・大寒(だいかん)
立春(りっしゅん)
| 2022年2月4日:2023年2月4日 |
|
| 意味:暦の上で、春が始まる日。まだ寒さは厳しいが初めて春の兆しが表れてくるころ。 |
| 太陽黄経:315度 |
雨水(うすい)
| 2022年2月19日:2023年2月19日 |
|
| 意味:降る雪が雨に変わり、積もった雪も解け始める。草木が芽吹き始め、早春の気配
が感じられるようになるころ。 |
| 太陽黄経:330度 |
啓蟄(けいちつ)
| 2022年3月5日:2023年3月6日 |
|
| 意味:陽気に誘われ、土の中の虫がはい出てくるころのこと。一雨ごとに春になっていくころ。 |
| 太陽黄経:345度 |
春分(しゅんぶん)
| 2022年3月21日:2023年3月21日 |
|
| 意味:太陽が真東から昇り、真西に沈む日のこと。昼と夜が同じ長さになる。 |
| 太陽黄経:0度 |
清明(せいめい)
| 2022年4月5日:2023年4月5日 |
|
| 意味:気候がしだいに温暖になり、すべてのものが清らかで生き生きするころのこと。花が咲き、鳥が歌い、生命が輝く季節の到来です。 |
| 太陽黄経:15度 |
穀雨(こくう)
| 2022年4月20日:2023年4月20日 |
|
| 意味:たくさんの穀物をうるおし、芽を出させる春の雨が降るころのこと。この季節の終わりには、夏の始まりを告げる八十八夜が訪れる。 |
| 太陽黄経:30度 |
立夏(りっか)
| 2022年5月5日:2023年5月6日 |
|
| 意味:暦の上で、夏が始まる日。新緑やさわやかな風に、夏の気配が感じられるようになる。 |
| 太陽黄経:45度 |
小満(しょうまん)
| 2022年5月21日:2023年5月21日 |
|
| 意味:いのちが成長して満ちてくるころのこと。草木も花々も、鳥も虫も獣も、日を浴びて輝く季節。 |
| 太陽黄経:60度 |
芒種(ぼうしゅ)
| 2022年6月6日:2023年6月6日 |
|
| 意味:「芒《のぎ》」とは、稲や麦などの実の殻にある針の形をした毛のこと。芒のある穀物の種 を蒔くころのこと。 |
| 太陽黄経:75度 |
夏至(げし)
| 2022年6月21日:2023年6月21日 |
|
| 意味:一年で最も昼が長く、夜が最も短い日。これから夏のさかりへと、暑さが日に日に増していく。 |
| 太陽黄経:90度 |
小暑(しょうしょ)
| 2022年7月7日:2023年7月7日 |
|
| 意味:梅雨が明けて本格的に夏になること。この日から立秋になるまでが、暑中見舞いの時期。 |
| 太陽黄経:105度 |
大暑(たいしょ)
| 2022年7月23日:2023年7月7日 |
|
| 意味:一年のうちで暑さが最も厳しいころのこと。 |
| 太陽黄経:120度 |
立秋(りっしゅう)
| 2022年8月7日:2023年8月8日 |
|
| 意味:暦の上で、秋が始まる日。暑い盛りだが、これ以降は夏の名残りの残暑という。秋が近いことを感じられるようになる。 |
| 太陽黄経:135度 |
処暑(しょしょ)
| 2022年8月23日:2023年8月23日 |
|
| 意味:「暑さが止む」という意味。このころから、涼しくなり始める。 |
| 太陽黄経:150度 |
白露(はくろ)
| 2022年9月8日:2023年9月8日 |
|
| 意味:大気が冷えてきて露を結ぶころのこと。ようやく残暑が引いていき、次第に秋らしい感じが増してくる。 |
| 太陽黄経:165度 |
秋分(しゅうぶん)
| 2022年9月23日:2023年9月23日 |
|
| 意味:春分と同じく、昼と夜の長さがほぼ等しくなる。これからしだいに日が短くなり、秋が深まってくる。 |
| 太陽黄経:180度 |
寒露(かんろ)
| 2022年10月8日:2023年10月8日 |
|
| 意味:冷気に当たって、露もこおりそうになるころ。木々も紅葉したり、落葉したりするようになる。 |
| 太陽黄経:195度 |
霜降(そうこう)
| 2022年10月23日:2023年10月24日 |
|
| 意味:朝夕にぐっと冷え込み、霜が降りるころ。寒さが増して、冬が近づいてきたことを感じられるようになる。 |
| 太陽黄経:210度 |
立冬(りっとう)
| 2022年11月7日:2023年11月08日 |
|
| 意味:暦の上で、冬が始まる日。木々の葉が落ち、冷たい風が吹き、冬枯れの様子が目立ってくる。 |
| 太陽黄経:225度 |
小雪(しょうせつ)
| 2022年11月22日:2023年11月22日 |
|
| 意味:寒さはまだ厳しくなく、雪もそれほど多くはないころ。冬の気配は進んでくる。 |
| 太陽黄経:240度 |
大雪(たいせつ)
| 2022年12月7日:2023年12月7日 |
|
| 意味:寒気が増し、雪も多くなってくるころ。冬の訪れを身にしみて感じるようになる。 |
| 太陽黄経:255度 |
冬至(とうじ)
| 2022年12月22日:2023年12月22日 |
|
| 意味:一年で最も昼が短く、夜が最も長い日。「冬至冬なか冬はじめ」といわれるように冬の中間地点にあたり、寒さの本番はこの後やってくる。 |
| 太陽黄経:270度 |
小寒(しょうかん)
| 2022年1月5日:2023年1月6日 |
|
| 意味:寒さがまだ最大まではいかないころ」という意味。この日から立春になるまでの期間を「寒《かん》」、小寒は「寒《かん》の入《い》り」ともいわれる。 |
| 太陽黄経:285度 |
大寒(だいかん)
| 2022年1月20日:2023年1月20日 |
|
| 意味:一年で最も寒い時期。二十四節気の最後の暦日。日がしだいに長くなり、春に 向かう時期でもある。 |
| 太陽黄経:300度 |
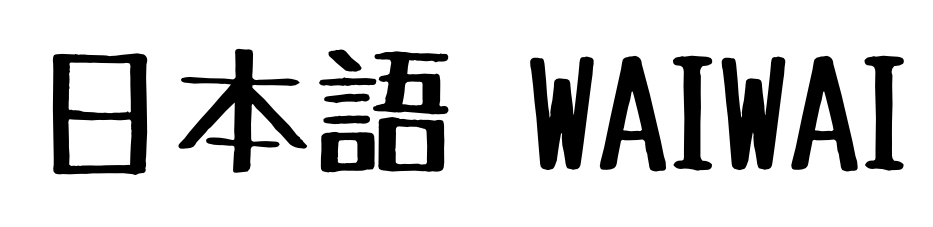

コメント